日本ではまだまだ定番とは言えない「ジン」というお酒ですが、欧米では主流な蒸留酒であり歴史にも深く関わっています。
ジントニックの様にカクテルとしては広く飲まれており、近年ではクラフトジンといったアプローチでも飲まれるようになってきています。
そんなジンですが本来は薬酒として飲まれており、その後世界中に渡って独自の文化を経てカクテルにまで昇華されていくこととなります。
その歴史を起源から詳しく説明します。
ジンを知るための基礎知識|蒸留技術とジュニパーベリー

それではまず、ジンという酒の基礎知識を説明します。
穀類を蒸留してできたアルコールにジュニパーベリーというボタニカル(草根木皮)で香りづけしたお酒を「ジン」と呼びます。
基礎知識を理解するうえでポイントとなるのが蒸留の技術とジュニパーベリーです。そしてジンの発祥がイギリスではなくオランダにあったという歴史も重要なポイントです。
スピリッツ
ジンはスピリッツの一種です。
水の沸点は100℃でアルコールの沸点は78.3℃ですが、蒸留の技術を利用すればこの沸点の差を利用して水とアルコールを分離することができます。
アルコールの沸点の方が低いので、加熱して先に出てくる蒸気を回収、冷却して液体にすればスピリッツと呼ばれる魔法の様なお酒が出来上がるのです。
ジュニパーベリー
ジンはスピリッツに香りづけをすることで出来上がります。その香りづけをしているのが「ジュニパーベリー」です。
ジンの起源は実はイギリスではなくオランダのフランドル地方(現在のオランダとベルギー)です。ここではスピリッツをジュニパーベリーで風味付けしたお酒を「ジュネヴァ」と呼んでいました。
オランダ人はオランダ東インド会社の設立により、約3万人の社員を世界中に派遣していました。当時、命取りとなっていた壊血病の予防としてハーブと一緒に飲まれていたのが「ジュネヴァ」だったのです。
「ジュネヴァ」はオランダ語で「ジュニパーベリー」を意味するもので、「ジュネヴァ」をイギリス人が英語化し、転じて「ジン」と呼ばれるようになりました。
この流れを理解しておくと、「ジン」とは「スピリッツにジュニパーベリーで風味付けしたお酒」という基礎知識が覚えやすくなるかと思います。
ジンの欧州間での変遷|ジンをイギリスへ持ち帰る

オランダで壊血病予防の薬用酒として飲まれていた「ジュネヴァ」ですが、その後イギリスへと拡まって「ジン・グレイズ(狂気のジン時代)」と呼ばれるほど社会に定着し、国民を堕落させる程に飲まれるようになります。
ジンをオランダからイギリスへ持ち込んだきっかけとなる人物がロバート・ダドリー伯爵です。
1500年代にイングランド軍を率いてオランダへ出兵しました。
その後も戦争は続き、その戦時中にイングランドの兵士たちはオランダで手に入れた「ジュネヴァ」を煽って戦いへの指揮を高めていたのです。
そして、そのイギリス人たちはジュネヴァの味を覚えて本国イギリスへ持ち帰ることになります。これがイギリスへジンが持ち込まれた歴史のはじまりです。
ジンの価格変動の歴史|ビールに重税がかけられる

17~18世紀当時のロンドンは、まさに近代の夜明け前といった時代で、人口は過密で労働需要の増大、賃金は上昇して消費の欲望が少しばかり増えていた頃でした。
そんな時代、1694年に当時も広く飲まれていたビールに重税がかけられることになりました。これによってジンの方が安いお酒になります。
ジンへの需要が高まりますが、ジュネヴァのモルトの様な複雑な味わいはその辺の蒸留所には出せず、低品質の穀類とあらゆる材料を混ぜて価格競争に走るようになってしまいました。
そして当時の労働者は貧しく、辛い労働とみすぼらしい生活を忘れるために安酒を飲むようになってしまいます。辛さを紛らわすことが目当ての消費者達は諸手を挙げて、低品質の安酒「ジン」を迎え入れてしまうかたちとなったのです。
当時は「ジン・グレイズ(狂気のジン時代)」と呼ばれるほど、ジンで堕落するイギリス人が街に溢れかえってしまい、本来は薬酒だったジンが「不道徳な酒」という印象に変容してしまったのでした。
ジンの全世界への普及|イギリスからアメリカの市場へ

その後、ジンは更に世界中に広まるようになります。そのきっかけはアメリカでの流行にありました。
次回はアメリカへ渡ったジンの歴史をご紹介します。ジンの歴史に大きな影響を与えたのは禁酒法です。
後編はこちらから
こちらはおまけの記事です。
気に入ったらツイートしてねTweet
参考文献:ジンの歴史 (「食」の図書館)/レスリー・ジェイコブズ・ソルモンソン
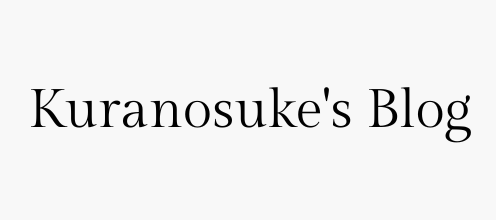






コメント