スコッチウイスキーは、その深い味わいと複雑な香りで世界中の愛好者を魅了しています。
中でも「ピーティー」と称されるスモーキーな風味は、スコッチの特徴の一つとして知られています。
この独特の風味は、「ピート」の影響によるものです。しかし「ピート」とは一体何なのか、なぜ「ピーティー」と呼ばれるのでしょうか。
本記事では、スコッチウイスキーの魅力を中心に、ピートの役割とおすすめのブランドを紹介します。
スコッチの世界を、より深く楽しむための一助としてお読みください。
ウイスキーの基本情報|スコッチウイスキーはスコットランド産

ウイスキーは世界各国で飲まれています。世界でも代表的な産地があり、一般的には「世界五大ウイスキー」と言われる5つの分類が存在します。
さらに詳しい情報やウイスキーの選び方については、Whiskey Spiritsで詳しく解説されています。
これらはウイスキー造りに適した産地の条件を備えており、多くの人々がウイスキーづくりに情熱をささげた深い歴史が存在する、非常に価値の高いブランドと言えます。
今回はスコットランド産の「スコッチ」をご紹介します。初めて飲む方にとっては、ツンとした香りに驚かれるかもしれません。
ピーティーなスコッチウイスキーとは何か?

「スコッチ」とはスコットランドで製造されるウイスキーのことを言います。
独特の香りが最大の特徴のウイスキーで、銘柄ごとに異なる様々な香りを楽しむことがスコッチの最大の魅力です。
日本では一般化される程には浸透していませんが、実は全世界のウイスキー生産のうち、約7割をスコッチが占めていると言われるほど世界的に有名なウイスキーなのです。
尚、スコッチウイスキーと同様に、バーボンも独特の風味と歴史で多くの愛好者を魅了しています。
特にアメリカ生まれのバーボンは、その製法や原材料に独自の特徴があります。このバーボンの詳しい背景や魅力については、バーボンの魅力と歴史で詳しく解説しています。
また、アメリカのウイスキーと言えばジャックダニエルが有名ですが、詳しくはジャックダニエル|なぜバーボンではないのか?で詳しく紹介しています。
これらの情報をもとに、さまざまなウイスキーを深く楽しんでください。
スコッチ独特の香りと魅力|「ピーティー」とは?

スコッチの最大の魅力はその独特のツンとした香りです。スコッチを初めて飲む人は「薬みたい」という感想を述べます。
その様な入門を経て味覚と嗅覚がスコッチに慣れてくると、だんだんとこの香りがたまらなくなってきます。
スコッチの独特の香りを「ピーティー」と表現することがあります。
「ピーティー」と言うのはスコッチの良い香りを指す表現で、スコッチ特有の製造過程にこの呼び名の由来が存在します。
スコッチの製造過程で使用する燃料は「泥炭」と言い、英語で「ピート(peat)」と言います。
スコッチは製造する過程で麦芽を乾燥させる工程が存在するのですが、その時に用いる燃料が「泥炭(ピート)」です。
ピートとは、シダやコケ、その他の植物類が堆積して年月を経ることにより炭化して形成される泥状の炭のことです。
麦芽を乾燥させる際にピートの香りが麦芽へ移ることから、スコッチ独特の香りが生まれるようになります。
スコットランドは寒冷な気候や多くの山脈や水資源など、地形的な要因でピートに恵まれていました。そしてピートは採取される産地によって含有される植物が異なるため、ウイスキーに移る香りにも違いが生まれます。
この様な経緯から「このスコッチはピーティーだね」と言う様な表現が生まれたのです。
ピーティーなスコッチのおすすめの飲み方

スコッチのおすすめの飲み方は何と言っても「ストレート」です。チェイサーを横に置いて交互に飲むことをおすすめします。また、温度も常温が良いとされています。
ストレートで飲むことがおすすめされる理由は、上述のピーティーな香りを楽しむためです。水で割ったり氷を入れると香りが薄まってしまうからです。
しかし、スコッチの爽やかな香りは冷たい炭酸の清涼感と非常に相性が良いので、個人的にはスコッチのハイボールも非常にお気に入りです。
香りを楽しみたい時はちょっと良いスコッチをストレートとチェイサーで、爽やかな気分になりたい時は良心的な値段のスコッチをハイボールにして頂く、というようにケースによって飲み分けると良いのではないでしょうか。
おすすめのピーティーなスコッチブランド
最後におすすめのスコッチをいくつかご紹介します。
グレンフィディック
スコッチのスタンダードとも言える存在で、世界シェアも30~40%と言われています。
これからスコッチを飲んでみようという方はグレンフィディックから始めてみることをおすすめします。
ラフロイグ
超強烈なピート香を楽しめる「ラフロイグ」。学生時代にスコッチ好きの友人宅で飲ませてもらい、その香りに驚いたことを今でも強く覚えています。
その強烈な個性は「好きか嫌いかどちらか」と言われているほど。一度このピート香を知ると、他では満足できなくなる中毒性があると思います。
ホワイトホース
日本ではキリンが販売をしているスコッチウイスキー。
ハイボールブームの流れもあり、日本市場専売の銘柄が多く存在します。もちろんこちらはハイボールで飲むのがおすすめで、近年では東京を中心に展開している立ち飲みチェーン「晩盃屋(バンパイヤ)」では「馬ハイ」という名称で飲むことができます。
ホワイトホースのハイボールで「馬ハイ」とはうまいこと考えたものです。価格が非常に良心的で庶民的な感覚で飲めるスコッチとしておすすめです。
気に入ったらツイートしてねTweet
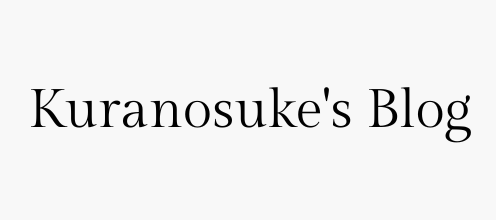






コメント