9月頃から11月頃まで、紅葉が色づいて秋が深まった頃に出荷される日本酒を「ひやおろし」と言います。
ひやおろしは一般的に貯蔵時と出荷前に行う火入れの工程を、貯蔵時の一回のみにして出荷前にはあえて火入れをしないという特徴があります。
そんなひやおろしと同じく火入れを一回だけにした日本酒に「寒おろし」があります。
日本酒の熟成サイクルから考えるとこの「寒おろし」は日本酒を最も熟成させて旨味が醸成された最終形態とも呼べる一品です。
年末の忙しさにかまけて「寒おろし」を見過ごさないよう気を付けましょう。
寒おろしの特徴|ひやおろしとの違い

「ひやおろし」と「寒おろし」はともに一度の火入れを経て製造されますが、「ひやおろし」は秋に出荷されるのに対し、「寒おろし」はさらに長い熟成期間を経た冬の日本酒として出荷されます。
具体的な出荷の時期は、寒さが訪れて冬の気配を感じる立冬(例年11月7日〜8日から約15日間)の頃です。
ひやおろしよりも数か月熟成期間が長いことになるので、旨味はより豊かになりまろやかさも完熟の域に達します。
冬の味覚にも相性の良い、心も身体もじっくりと温めてくれる日本酒なのです。
寒おろしの入手方法|新酒と同時に店頭に並んでいる

秋めいてくると酒屋などでは「ひやおろし」の文字をよく目にするようになりますが、「寒おろし」はひやおろしほど世間に認知されていません。
それは何故か。推測ではありますが、日本酒が製造されるサイクルは一年を通した工程で行われますが「寒おろし」が出荷される頃には、もう既に翌年の新酒も出荷される時期なのです。
新酒の生酒を「しぼりたて」と呼び、僕は例年ついつい「しぼりたて」を見つけては購入してしまいます。「しぼりたて」が「寒おろし」を見えにくくしているのかもしれません。
本来立冬の季節以降は「寒おろし」の熟成された旨味と「しぼりたて」のフレッシュな味わいを飲み比べることができる、日本酒好きとしてはとっても貴重な季節です。
せっかくの機会なので季節ごとの日本酒を楽しむべく、冬の夜長に「寒おろし」をぜひお試しください。
気に入ったらツイートしてねTweet
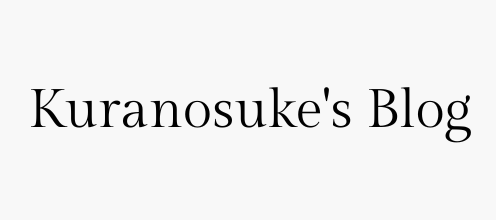



コメント