カレー(curry)という言葉は、起源であるインドではもともと使われていませんでした。
今でも「カレー(curry)」と呼んでいるのは外国人側であり、国内外で少し感覚が異なっているようです。
それでは一体、カレーの語源は何なのでしょうか。
カレーの名前の起源|インドの「カリ」

「カレー(curry)」という言葉の起源についてはたくさんあるようですが、南インドのカリル(karil)またはカリ(kari)という言葉がもとになっている説が最も有力だと言われています。
いずれも「スパイスで味を付けた野菜や肉の炒め物」といった意味で使われていたようです。現地人がカリルやカリと呼んでいたこれらの料理を、ヨーロッパ人が料理名だと勘違いしたことが発端です。
そして「カリル」も、ヨーロッパ言語のなかでのスペルは長い歴史をかけて少しずつ変化していったようで、下記のように段階的な経緯で現在の「curry(カレー)」まで至っています。
karil→caril→curress→curey→curry(カレー)。
今ではインド人も家庭で作る煮込み料理全般のことを、特に外国人向けでは「カレー」と呼ぶようになったようですが、そもそもはヨーロッパ人の勘違いがもとになったというのは面白い歴史だと言えます。
それでは、カリール(karil)からカレー(curry)になるまで、どの様な経緯を辿ったのでしょうか。
カレーの語源とその最初の記述|インド人はカリールをつくる

インドで植物や香料の研究をしていたポルトガル人の医師がいます。彼の名はガルシア・ダ・オルダ。
彼が1563年に出版した著書『インド薬草・薬物対話集』の中で、「インド人が”カリール”という料理を作る」という記述があります。
これがヨーロッパの文献に登場する最初の「カレー」です。
ポルトガル人であることから、その時に出会ったカレーはゴア地方のカレーであるかと思われます。
カレーの進化|煮込み汁は「なかなか美味しい」

その後、オランダ人の旅行家ヤン・ホイフェン・ヴァン・リンスホーテンが1595年~96年に『東方案内記』という本を出版します。
この本にカレーのことを下記のように書き残しています。
「魚はたいていスープで煮込み、米飯にかけて食べる。この煮込み汁をカリール(caril)という。やや酸味があって、クライス・ベス(酢ぐりの一種)か未熟なぶどうでも混ぜたような味。なかなか美味しい。」
『東方案内記』ヤン・ホイフェン・ヴァン・リンスホーテン
実際にヨーロッパ人がカレー(カリール)を食べて「なかなか美味しい」と言及しています。
カレーはこの当時から美味しかったのかもしれません。
カリール(caril)からカレー(currees)へ|ご飯にかけるものである

17世紀になるとイギリス人の医師ロバート・ノックスが『セイロン島誌』という書籍を発表します。
ここでは下記のような記述がされています。
「彼らは果実を煮て、ポルトガル語で言うカレー(currees)をつくる。これは何かご飯と一緒にして、かけて食べるためのものである。」
『セイロン島誌』ロバート・ノックス
ポルトガル語、オランダ語を経て、ようやくこのあたりで英語圏であるイギリスに「currees」という言葉まで変化していった様子が見て取れます。
その後、イギリスとインドでは外交関係が続き、カレー粉の開発という歴史的に重要な役割を果たすこととなります。
カレー(currees)はついにカレー(curry)になった

その後、ハナ―・グラスという著者の書籍『明解簡易料理法』という本が1747年に出版され、そのなかについに「カレー(curry)」というスペルでカレーが記載されます。
語学を勉強したことがある方は、こういったかたちで言語が長い時をかけて受け継がれていく様を学んだことがあるかもしれません。
カレーもそういった長い経緯があったようです。あらためて歴史深い食べ物なんだなと再認識しました。
参考文献:カレーの世界史/井上武久
気に入ったらツイートしてねTweet
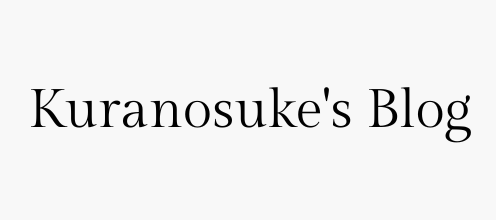



コメント