1935年に日本において新しいカレーのメニューが誕生します。みなさんご存知の「カレーうどん」です。
もともとはインド発祥だったカレーも、遂に日本ではここまで独自の変化を遂げたことになります。発祥は東京都新宿区の老舗蕎麦屋でした。
カレーうどんの基本レシピ

カレーうどんの調理方法は、和風だしのつゆをベースにカレー粉を溶いて、片栗粉でとろみをつけたスープをうどんにかける方法が一般的です。
しかし調理法は多種多様であり、茹でた麺にカレーライス用のカレーを直接かけたものなどもあります。いずれのカレーうどんが出てきても、特に気にせずに「カレーうどん」として多くの人が食するでしょう。
お店ごとに多様なレシピが受け継がれている食文化なので、そういった側面も楽しんで食べに行くともっと楽しくなるはずです。
さて、そんなカレーうどんですが、そもそもどういった経緯で誕生したのでしょうか。
カレーうどんの誕生|なぜ誕生したのか?

1935年に東京都新宿区の早稲田大学付近にあった「三朝庵」という蕎麦屋でカレーうどんは生まれました。
当時カレーライスは高級でハイカラな人々が食べるものであり、決して庶民的な食べ物ではありませんでしたが、新しいもの好きであった「三朝庵」の開業者朝治郎さんが、何か新しい物はできないかと材料屋に持ちかけたことが発祥と言われています。
もともと庶民のメニューだったうどんに当時の新しい流行を取り入れたわけです。
「うどん」という日本人の庶民のメニューに掛け合わせることで、ハイカラでエキゾチックな存在だったカレーが、一気に身近な存在になったことは想像に難くありません。
名古屋カレーうどんへの伝播|「名古屋めし」に進化

東京都新宿で誕生したカレーうどんは、その後全国的に広がり、西の大都市である名古屋まで伝播されることになります。
1976年創業の「本店 鯱乃家」(しゃちのや)という名古屋のお店が、独自の製法でカレーうどんを作り上げ、それが名物料理となり人気を集めたことが始まりです。これに対抗すべく既存の店舗も競うように名古屋カレーうどんの文化を昇華させていきました。
名古屋カレーうどんは、まずスープに特徴がありラーメンスープに使用される鶏ガラスープがベースとなっています。
そこにインドカレーの様に何種類ものスパイスを独自にブレンド、さらに魚介類系の和風だしを加えたカレールウが出来上がります。
カレーうどんというと日本独自の温かみのある味わいが想像されますが、ラーメンスープとインドカレーばりのスパイシーなルウといった、ある意味インドへ逆輸入したような存在なのです。
尚、カレーのスパイスの主成分はターメリック(ウコン)であることから、名古屋カレーうどんは二日酔い防止にも効果があると評判で、飲み会のシメにカレーうどんを食べる文化があるようです。
こうした独自の文化が醸成されているのは非常に興味深い現象です。うどんをすすってはねたカレーが白いワイシャツに付いてしまう文化も愛着が持てますね。
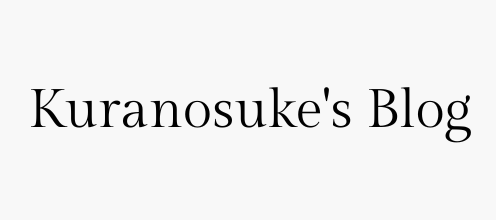



コメント